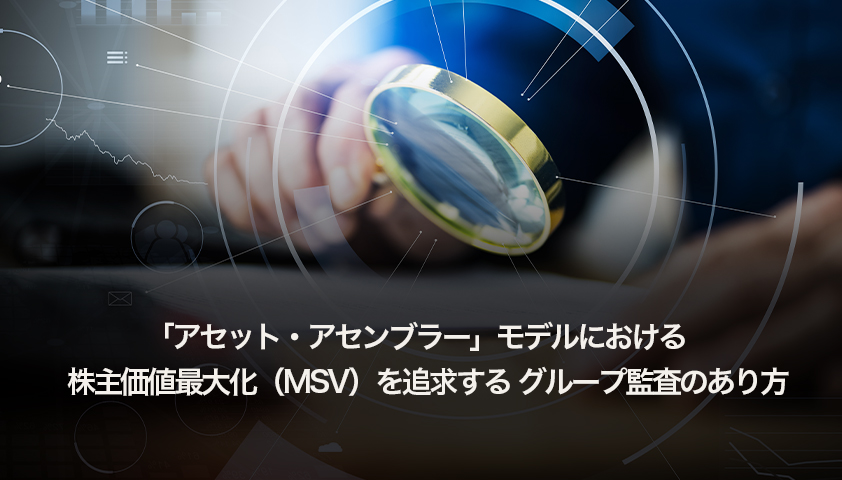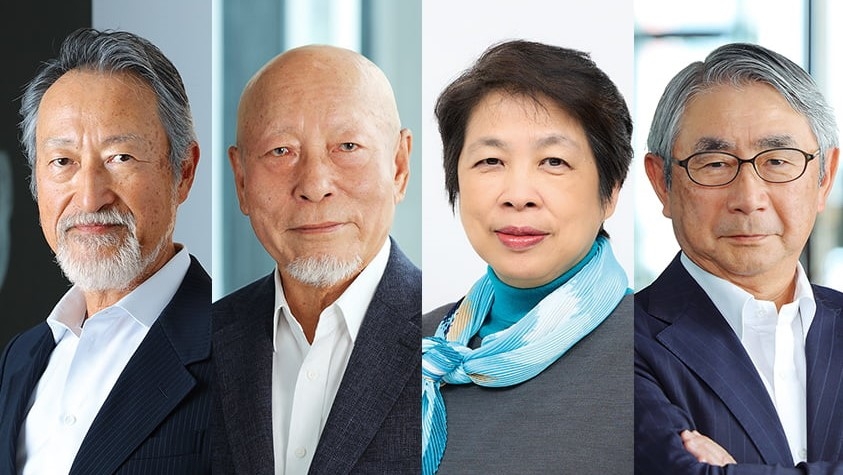独立社外取締役への質問(一問一答)
投資家の皆さまとの対話を通じていただいたガバナンス関連のご意見やご質問に、筆頭独立社外取締役の中村昌義がお答えします。
代表執行役共同社長の報酬について
-
ご質問にお答えする前に、代表執行役社長の指名・報酬プロセスを含む、当社の志向するガバナンス体制は株主の皆様との価値共有、とりわけ少数株主利益の保護を前提としていることについて触れておきたいと思います。
当社は経営の透明性・客観性・公正性の向上や執行と監督の分離・強化を目的として、2020年に指名委員会等設置会社に移行しました。加えて、より高度なガバナンス体制を志向し、独立性や実効性の向上を図るべく、取締役会において独立社外取締役が過半数を占め、議長も務めています。また、各委員会においても独立社外取締役が過半数を占めるとともに委員長を務め、非業務執行取締役のみで構成することで、執行からの独立性を確保しています。さらに、独立社外取締役の報酬の概ね半分は譲渡制限付株式報酬で構成されており、独立社外取締役はより株主の皆様に近い目線で執行側を監督しています。
このようなガバナンス体制のもと、指名委員会による答申に基づき、取締役会の決議を経て選任される代表執行役社長は「株主価値最大化(MSV)」の追求に最適と考えると同時に、報酬についても報酬委員会は代表執行役社長が持てる能力を最大限に発揮し、MSVの実現に資する報酬決定に努めています。
その上で、「共同社長の報酬総額を具体的にどのように決定しているのか?」についてですが、2023年9月末に発行した「統合報告書2023」の報酬委員会報告(P111-112) でもご説明している通り、MSVの実現に向けた財務・非財務面における共同社長のパフォーマンスの総合的な評価や、さらなる飛躍へのモチベーションが働く報酬について、報酬委員会において議論を重ね、決定しています。
具体的に2022年度のパフォーマンスについては、財務面では当社における業績の推移のみならず、外部環境や市況を踏まえて客観的に確認するべく、競合他社比較での売上収益、当期利益成長率、MSV指標(EPS、PER)などに基づき総合的に評価しました。例えば、グローバル塗料売上高トップ6社(当社のポジションは第4位)のうち、共同社長体制移行後の2022年までの2年間におけるEPSの年平均成長率(CAGR)は10.2%と表示通貨ベースでは第1位であり、2位を約5ポイント上回っていること、2022年度末時点のPER※1はLTM(Last Twelve Months)で32.1倍、NTM(Next Twelve Months)で24.6倍とどちらも第1位であり、当社の掲げるMSVの追求の成果として高く評価しました。
また、非財務面では既存事業の収益性や体質改善、新規アセットの積み上げを中心とした成長戦略構想、「アセット・アセンブラー」モデルに基づくサステナビリティ体制や人的資本の強化、効果的かつ効率的な執行側ガバナンス体制、すなわち内部統制システムの強化に向けた進捗を確認し、これらを総合的に評価しています。例えば、ウィー共同社長については、中国不動産市場のリスクと当社への影響について早期から注視し、現地会社と綿密な情報共有、対応の検討を進めるとともに、継続的に取締役会へ報告し、適切なリスクマネジメントを図っていたこと、収益性が軟調な日本セグメントの体質改善や技術人材・体制の強化、船舶用事業のコスト構造の適正化や組織最適化による収益性改善などの既存事業の価値向上などについて評価しました。若月共同社長については、中長期的なM&A戦略について取締役と定期的に共有し、欧州塗料メーカーであるCromology社やJUB社などのMSVにつながるM&Aを着実に進めるとともに、市場流動性の向上やグローバルな投資家基盤の構築を目的とした海外市場における株式売出し、リスクマネジメント・サステナビリティ体制の構築・強化による「自律・分散型経営」の高度化などを評価しました。
このように、事業や社会環境が激変する不安定な現状において、MSVの中長期的な実現に資する機会を逃すことなく、適切なリスクを負って果敢に推進することは極めて重要であり、両共同社長の評価において単年度の業績と同等以上に重視しています。
また、これらの評価は独立社外取締役会議や指名委員会でも共有され、報酬決定のみならず代表執行役社長の適切な選解任にもつなげています。その上で、次年度もMSVの実現に資すると信任した共同社長のモチベーションを維持・向上させる報酬とするべく、パフォーマンスの評価と併せて既存の報酬や競合他社の報酬動向に鑑み、報酬総額を最終決定※2しています。
続いて、「株式報酬をなぜ共同社長に付与しないのか?」については、独立社外取締役や投資家の皆様を中心とした資本市場のご意見も参考にし、報酬委員会にて株式報酬の有無も含めた報酬構成について継続的な議論を行っています。現在、共同社長に株式報酬を付与していない主な理由は、株式報酬を付与することが当社成長の原動力となる共同社長の適切かつ果断なリスクテイクの促進やモチベーションのさらなる向上に必ずしもつながらないと考えているためです。
株式報酬は株主の皆様との中長期的な価値共有を図る手法の1つと考えますが、中長期的な成長や貢献を適正に反映し得る評価項目や期間の設定、株式の付与方法、売買の制限、その間の株価変動により、報酬としての価値やインセンティブ性が変化することなどを考慮する必要があり、非常に複雑性の高い報酬です。私たちは、共同社長の推進する「アセット・アセンブラー」モデルの優位性を生かし、激変する不安定な環境下においても財務健全性を確保し、機会を逃すことなく適切かつ果断にリスクを取り、MSVを追求することを共同社長に課しています。株式による報酬は当社の業績や取り組みのみならず、結果的に世界経済や社会問題などの外部環境に影響され、大きく変動することが考えられます。そのため、本人が考えている貢献や評価と一致せず、効果的なモチベーションの維持・向上につながらないこともあり、当社の現状において株式報酬を含む報酬構成は、適切なリスクテイクを促す私たちの意志を貫くためには必ずしも最適ではないと考えています。他方、前述のガバナンス体制のもと、当社の共同社長報酬は、MSVの実現に向けた評価に基づく指名・報酬決定を厳格に行っていくことにより、株主の皆様との価値共有を十分に果たしていると考えています。
なお、共同社長報酬の決定においては、競合他社のCEO報酬水準も考慮し決定しています。当社を除くグローバル塗料売上高トップ6社の2021年度、2022年度のCEO平均報酬総額※3は約11.5億円であり(うち株式報酬は約8.3億円、報酬総額の72.4%)、各年の最も高額なCEOの平均報酬総額※3は約17.1億円(うち株式報酬は約12.6億円、報酬総額の73.9%)となっており、株式報酬が報酬全体の70%以上を占めています。これに対し、株式を含まない当社の共同社長の2022年度報酬総額※4は、ウィー共同社長が約7.2億円、若月共同社長が約4.0億円ですが、共同社長が当社の成長を力強くけん引している実績に鑑み、MSVに資するものと考えています※5。
今後も私たちは報酬委員会を中心に、当社の状況や外部環境の動向を踏まえた議論を重ね、株主の皆様との価値共有を前提としたMSVの実現に資する共同社長報酬を追求してまいります。
※1 出所:FactSet(2022年12月30日時点)
※2 「2021年度の通期業績において税引前利益は前年対比で減益であったが、2022年度の若月共同社長の報酬が増えた理由についてお伺いしたい」というご質問をいただいています。2021年度の税引前利益は短信ベースで前年対比約30億円の減益となっていますが、これには一過性費用約78億円(インドネシア事業買収に伴う印紙税・PPAに伴う棚卸資産のステップアップの費用化、国内再編プロジェクト費用、子会社株式の段階取得による差損など)を含んでいます。したがって、財務面において前年と比較して劣ったとは評価していません。
※3 国や会社によって背景の異なる年金や退職金、福利厚生費用などは報酬から除き、各年末時点の為替レートを用いて算出。2022年度については期中辞任の1社を除いて算出。
※4 出所:2022年12月期 第197期 有価証券報告書
※5 なお、共同社長就任後の自己資金による購入を含め、2023年6月末時点でウィー共同社長が100,000株、若月共同社長が180,110株を所有しています。
サステナビリティ
-
当社は、経営上の唯一のミッションとして「株主価値最大化(MSV)」を掲げています。その実現に当たっては、顧客・取引先・従業員・社会などへの責務を充足することが大前提です。この「責務の充足」は法的な契約のみならず、社会的、倫理的責務の充足にまで及び、これらを欠いては私たちの目指すMSVを実現することはできません。
本稿で2023年6月30日に公開した「「アセット・アセンブラー」モデル」において、共同社長が推進する「アセット・アセンブラー」モデルにおけるリスクマネジメントの一翼として、当社のサステナビリティ体制をご紹介しました。
この体制のもと、各サステナビリティ・チームは、気候変動をはじめとする地球規模の課題や将来に向けて行動すべき社会課題などをテーマにそれぞれ活動しています。グループの内部統制システムに基づき各PCG(地域・事業ごとの会社群)が現場を起点に自律的に取り組むリスクマネジメントに加え、これらの各サステナビリティ・チームが推進するグローバル活動は、競合他社に先駆けて将来課題や社会的要請に応えることを通じて当社の存在意義を向上するとともに、競争力を増強することに貢献します。
今回は、この「アセット・アセンブラー」モデルに基づくサステナビリティ体制に焦点を当て、その背景や現在の私たちが感じている手応えについてご説明します。
現在のサステナビリティ体制は、共同社長が率いる5つの自律的なサステナビリティ・チームによって構成されています。それらは、当社が特定しているマテリアリティに直結する「環境&安全」「人とコミュニティ」「イノベーション」の3つのチームと、それらを横断する「ガバナンス」「調達」の2つのチームです。各チームは、それぞれのテーマに長けたビジネスリーダーを中心に各PCGのエキスパートを集めてグローバルな取り組みを進めています。
チームリーダーは共同社長に対して進捗や提案を直接報告し、共同社長はサステナビリティ活動の状況について適宜取締役会へ報告しています。これらを通じ、私たち取締役会は、マテリアリティに関するリスクと機会を中長期的な観点から包括的に把握し、「アセット・アセンブラー」モデルのもと、MSVに向けて執行が果敢に取るリスクテイクをサポート・監督しています。
現在のマテリアリティは、「環境&安全」チームがテーマとする「気候変動」「資源と汚染」「労働安全衛生」、「人とコミュニティ」チームの「ダイバーシティ&インクルージョン」、「コミュニティとともに成長」、「イノベーション」チームの「社会的課題を解決するイノベーション創出」の6つです。これらは当社が指名委員会等設置会社に移行した2020年に定めたものです。主要パートナー会社(PC:当社の連結子会社)から適切な委員25名を選定したESG委員会を組成し、ステークホルダーにとっての重要度と当社グループにとっての重要度を2軸とする検討を通じて、2020年8月の取締役会にて特定しました。(「マテリアリティ」参照)
その後、2021年4月の共同社長体制へ移行を基点に、「アセット・アセンブラー」モデルに基づくガバナンス体制へと整備が進むに伴い、サステナビリティ体制も併せて一新し、本社主導ではなく、MSVをゴールとする現場・ビジネス主導の自律的体制に移行しました。
グループ横断で取り組むべき課題に対し、本社主導でテーマを設定・計画立案し、それを上意下達で子会社に徹底・管理する方式は、グローバル一律で中央集権的な管理を志向するグローバル企業で広く見受けられます。他方、私たちが追求するMSVにおいては、各地域・市場に根差した各PCGの自律性に基づくサステナブルな成長が鍵となります。私たち取締役会は、テーマ設定・進捗管理する当時のESG推進部と実際の現場でビジネスを営むPCの間に生じるタイムラグや認識の差異が、MSV実現を将来的に阻害する可能性を懸念し、中央集権的な本社主導の管理から、相互信頼に基づく各PCGの自律性を尊重する自律的なサステナビリティ体制への改編を合理的と判断しました。
従前は、各テーマの社会的な要請に対して本社が取り組みを主導・推進していましたが、現体制においては各テーマに造詣が深く、実際に今この瞬間もそのテーマを追求しているチームリーダーが組織の垣根なく選抜されています。これにより、社会的な責務を果たすだけでなく、事業機会を見いだし、新市場に参入するなど、当社ビジネスに直結させることがより一層可能となりました。
さらに、自律的なサステナビリティ体制への移行当初は、現在の「調達」チームを除く4チームによる構成でしたが、翌2022年7月には、「人権問題」への社会的関心の高まりを受け、「ガバナンス」チームからサステナビリティ体制の中でこの課題を取り組むことが提議されました。それを受け、「倫理的調達」を横断的活動の端緒とし、長期安定的な原料・資材の調達に向けて「調達」チームを新設し、現在の5つのチーム構成としました。
これらのグループ施策の進化に臨み、取締役会は、執行側で掲げていた「ESGステートメント」に替え、「サステナビリティ基本方針」を共同社長とともに今年2023年3月に制定しました。これにより、当社の標榜するMSVをゴールとするサステナビリティ活動の位置付けが明確になり、当社グループの目指す方向を改めて共有できました。
2023年7月に開催した取締役会において、現行の自律的なサステナビリティ体制に移行してから2年が経過していること、本年度は次期中期経営計画の策定年度であることも勘案し、5つのサステナビリティ・チームの主要メンバーを招聘し、各チームのテーマ群についてディスカッションを行いました。取締役会では毎回共同社長レポートの枠があり、その中で共同社長からサステナビリティ関連の報告を受け、適宜審議していますが、5名のリーダーや主要メンバーが一堂に会して審議する機会は初めてのものになりました。各チームの体制や進捗、今後のスケジュール、課題などについて率直な意見交換が行われ、取締役、各チームともに、当社グループが推進するサステナビリティ活動の全体像を把握することができました。加えて、社会的要請と地域の特性を熟慮しつつ、ビジネスニーズに対する適応性を確保するべく、各PCGが柔軟かつ多様な活動を展開していることを改めて確認することができました。
なお、取締役会での議論の概要については、近日発行予定の統合報告書にてご紹介予定です。そちらもご参照いただくことをお願いいたします。
取締役会の議論を通じて、課題に向けた各チームの真摯な取り組み、堅実に前進する姿勢に触れ、私たち取締役の理解は一層深まりました。私個人の心象としては、各チームが何におもねることも取り繕うこともなく、実直な計画に基づいて着実に取り組んでいる姿が印象的で、率直に安心しました。そして、彼らにリーダーシップを託した共同社長の手腕についても改めて評価しています。
当社の「アセット・アセンブラー」モデルは、取締役、共同社長、PCの経営陣、従業員のそれぞれの相互信頼をベースに成り立っています。今回のサステナビリティに関する個々のテーマを巡る対話を通じて、当社のサステナビリティ活動は、相互信頼を醸成する5つの共通言語となっていることが改めて認識されました。
「アセット・アセンブラー」のモデルのもとで現場・ビジネスを主導に推し進めるサステナビリティ活動は、将来の変化を見据えてさらに深化し、MSV実現への歩みを進めてまいります。
「アセット・アセンブラー」モデル
-
共同社長が推進する「アセット・アセンブラー」モデルは、相互信頼に基づく「自律・分散型経営」をベースに「株主価値最大化(MSV)」を追求するものであり、各パートナー会社(PC:当社の連結子会社)はそれぞれの経営陣のもとでサステナブルな事業成長を自律的に邁進しています。
リスクの多くは現場に潜んでおり、最も実効的なリスクマネジメントを実践できる主体は、純粋持株会社である当社ではなく、地域・市場に精通した各PC自身です。現在、各PCは塗料・コーティング分野のみならず、さらにその周辺分野(Paint++)へと事業領域を押し広げていますが、これらの分野は比較的地域性が強く、地産地消型の自律的な事業展開が適しています。現在、当社グループは45ヵ国・地域でビジネスを展開し、海外売上収益比率は80%以上、従業員数は約33,000人を数えます。グループ全体でサステナブルな成長を継続し、MSVを追求するためには、私たちが選び、信頼している各PCの経営陣による自律的な成長力を最大限に発揮させる環境を整えることが肝心であり、それが持株会社としての当社のリスクマネージの実効性を高めると考えます。私たち取締役会は、各PCとの相互信頼に基づき、彼らの自律的な成長を尊重しつつ、グループ全体のリスクを適切にモニタリングし、対処しています。
こうした相互信頼に基づく自律・分散型経営による「アセット・アセンブラー」モデルが機能するためには、共同社長のもとで各PCによって執行される内部統制が、グループ全体のリスクマネジメントとして実効的であると、私たちが常に確認できることが大前提です。そこで、取締役会は、共同社長とともに、「アセット・アセンブラー」モデルの有効性を強化するために、2021年度にグループ内部統制システムを刷新しました。
再構築した当社のグループ内部統制システムにおいて、共同社長によって率いられる執行側のガバナンスは、「グローバル行動規範」、「内部統制システム基本方針」に従う「グローバル・リスクマネジメント基本方針」、「内部通報窓口グローバル基本方針」を核として構成しています。それぞれについて、簡潔にご説明していきましょう。
まず、基点となる「グローバル行動規範」です。当社グループに属する全員が共有し、遵守すべきコンプライアンス、倫理、サステナビリティに関する規範として、誠実な行動、協働、コミュニティ・環境への貢献について、22項目の「Do」と「Don’t」を策定しました。この起草に際しては、共同社長のリーダーシップのもとで国内外の主要PC責任者の積極的なコミットメントを引き出しつつ、コンプライアンス、ファイナンス、人事部門のトップが参集する中、各地域・市場における将来のビジネスを見据えつつ、グローバルな視点で議論を行いました。当社がトップダウンで一方的に制定したのではなく、各主要PCとともに策定したものであるからこそ、各国・地域へ幅広く受け入れられ、浸透されるものとなったと考えます。
続いて、刷新を行った「内部統制システム基本方針」においては、取締役会が共同社長へ可能な限り執行に関する権限を委譲することを定めたことに加えて、各PCを地域・事業ごとのPC群(PCG)に区分し、共同社長が各PCGの責任者に対し、相互信頼に基づき、各PCGの業務執行の権限と内部統制に関する責任を委ねることによって、各PCGの自律的成長の最大化を目指すと明示しています。
この「内部統制システム基本方針」に従い、「グローバル・リスクマネジメント基本方針」や、各PCGの内部通報窓口の設置・運営について定めた「内部通報窓口グローバル基本方針」の改定も行いました。
この「グローバル・リスクマネジメント基本方針」に則り、2022年度からPCGへのアシュアランスプロセスが実施されており、この中でリスクアセスメント調査(Control Self-Assessment (CSA))も行われています。各PCG責任者は、「グローバル行動規範」に基づき共有された価値観のもと、内部統制上の重要項目が網羅されているCSAのリスク項目について自己点検し、自律的に評価するのみならず、自らが認識する5大リスクを挙げるとともに、必要な対策を共同社長に提示することが求められます。共同社長は、各PCG責任者からの報告を踏まえ、グループリスクを地域・事業ごとに把握し、各PCGの重要な経営会議体への直接参加などを通じて、実効的なモニタリング、必要なリスク対応を指示しています。これらの結果は、監査委員会で審議された後、取締役会にも報告されます。
また、これと並行して、「内部通報窓口グローバル基本方針」に従って、各PCGは自らの内部通報窓口の整備を自律的に進めており、各地での通報の状況を共同社長に報告しており、それらは監査委員会、取締役会でも確認しています。
他方、上述のような共同社長のもとで各PCGの自律性を尊重するグループ内部統制の仕組みを整えることのみでは拾いあげられない、各PCG共通・横断で取り組むべき、あるいは、PCG単独の現場主導では解決できない課題やリスクも存在します。
これらの代表格は、当社が特定している「気候変動」、「ダイバーシティ&インクルージョン」、「社会課題を解決するイノベーション創出」をはじめとする6つの「マテリアリティ」に関するものであり、この他にも、グローバルな世論やビジネス環境の変化、競合動向によって今後生じるものもあると考えます。
こうした課題やリスクへの対応として、共同社長のリーダーシップのもと、2022年よりサステナビリティ体制を一新し、マテリアリティをベースとしたサステナビリティ・チームを組成しています。ここにおいても、当社主導ではなく、サステナビリティとビジネスとの結び付きをより強化する自律的なチームとして立ち上げ、各テーマに長けたビジネスリーダーを中心にグローバルな取り組みを進めています。
2022年当初は、マテリアリティに対応した「環境&安全」、「人とコミュニティ」、「イノベーション」と、より横断的な「ガバナンス」の4つのチームでしたが、2022年下期には、調達における人権問題を含む倫理的調達に関する取り組みもマテリアリティ横断で強化すべきとし5チーム構成となりました。
また、私たち取締役会は、共同社長とともに、これらの当社グループのサステナビリティ活動が、「アセット・アセンブラー」モデルを通じてMSVを追求する前提であり、MSVをゴールとするものであることを改めて認識するとともに、それを「サステナビリティ基本方針」として策定・公表しています。
このように刷新されたグループ内部統制の枠組みとサステナビリティへのアプローチは、共同社長のイニシアティブによって各PCGに徹底されており、強固な相互信頼を構築するバックボーンとなっています。さらに、各PCGにおける監査機能が、各PCGの執行側のガバナンスの運営状況を監査し、それら各PCGの自律的監査の枠組みが適正に機能しているかを当社の監査委員会が監督する「Audit on Audit」体制とすることで、グループ全体での内部統制の実効性・効率性の向上を図っています。
以上が、私たち取締役会が「共同社長のもと、各PCによって執行される事業運営を適切にモニターし、しかるべき牽制機能を通じてグループリスクへの対応を行う責務」を、相互信頼に基づく各PCの自律性を尊重する「アセット・アセンブラー」モデルにおいて果たす体制となります。
相互信頼に基づく「自律・分散型経営」をベースにMSVを追求する上で、適切なリスクマネジメントは非常に重要であり、私たちは、これからも絶えず世の趨勢やグループ内部統制の状況などを注視し、あるべき体制・仕組みの整備・更新を行っていきます。
ガバナンス上の問題、課題
-
当社グループのガバナンス上の最大の課題は、「株主価値最大化(MSV)に向けてタイムリーかつ適切なリスクを執行が果敢に取り続けられるか」にあります。
現在共同社長が推進する「アセット・アセンブラー」モデルは、以前当社が志向した「蜘蛛の巣型経営」の進化形であり、グループ内の相互信頼に基づく「自律・分散型経営」をベースにMSVを追求するものです。当社はこの経営モデルに基づき、既存ビジネスのさらなる成長に加え、買収による将来の成長機会を求め、優れた経営陣によってけん引される優良なアセットをさらに積み上げていきます。
当社の既存のアセットである各パートナー会社では、共同社長のリーダーシップのもと、昨今の厳しい外部環境下においてもそれぞれの経営陣が敏速に事業を推進しています。私たち取締役会は、この執行からの求めに対し、そのスピードを減速することがなきように十分にその真意を理解し、適切な監督・サポートを続けなければなりません。また、新たなアセットを積み上げる機会を見逃さぬよう、買収戦略について常に執行と意見を交換し、方向性を共有しておくことが不可欠です。既存のアセットの価値向上、新しいアセットの積み上げに向けては、いずれも財務規律を守った上で、資本市場からの理解を醸成することがMSV追求の道であります。
この実現のためには、取締役会における監督と執行の間の信頼関係が最も重要です。指名委員会等設置会社である当社は、大幅に執行へ権限を委譲しており、その前提は自信を持って執行を信頼することにあります。取締役が執行を信頼できなければ、取締役として、監督の責務を果たすためにリスクを細部にわたって把握し対処せざるを得ず、執行への過干渉になり、判断を遅らせ、ひいては成長機会を逃すことにつながります。他方、執行を盲目的に信頼し提案を追認するのみでは、リスク評価を誤り、回避の機会を逃し、やはり次の成長機会へのアクセスができなくなります。加えて、適切な助言が得られないのであれば、執行から監督への信頼が生じる余地はなく、全うに自らの戦略に関して取締役会にチャレンジし、審議を通じてさらに良いものにしていこうとの動機は消失し、自らの責任の範囲内で可もなく不可もない施策にとどめた方が無難との心象を抱くかもしれません。
この匙加減が非常に難しいところです。当社の指名委員会は、取締役一人ひとりの「事業会社経営経験」、「グローバル経験」、「M&A経験」を重視しています(本稿で2023年2月28日に公開した「取締役の人数およびスキル・マトリックス 」参照)。私たち取締役は、執行の責任者として直面した事案のリスクを細部にわたって分析・洞察し、許容度を測り、自身の責任において結果にコミットした上で、そのリスクを取って実行した経験、または、断念せざるを得なかった経験を持ち合わせています。このようなバックグラウンドを持つ私たちは、執行への過剰な関与に傾くことなく、案件のクリティカルポイントを明確にあぶり出し、的確な助言を行うことを常としています。グループ内外の最新情報を常時把握する必要もあり、胆力の要る責務です。また、取締役会と同じ頻度で開催している独立社外取締役会議では、さまざまなトピックについて意見が交換され、独立社外取締役としての独立性を維持するとともに、互いの信頼を高めています。
ここでは、2022年1月に実施した普通株式売出し※を例に、私たち取締役会がどのようなガバナンスを志向しているかをご紹介し、取締役会議長として当社グループのガバナンス上の最大の課題を「MSVに向けてタイムリーかつ適切なリスクを執行が果敢に取り続けられるか」と捉えていることの真意を補足したいと思います。
時価総額に比べて低い当社株式の市場流動性の向上は財務戦略上の大きな課題の一つであり、執行側も長らく解決の糸口を探っていました。売出人である金融機関6社の売却意向は伺っていたものの、買収案件等を常に検討している当社にとって売出しの機会は限られていました。この時期は新型コロナウイルスの流行による世界的なサプライチェーンの混乱によって、資本市場の株価が当社を含めて停滞または低下傾向を示しつつある時期でもありました。売出しによる一時的な需給悪化によるさらなる株価下落を招く懸念もあり、非常に判断が難しい状況でしたが、私たち取締役会は、執行が売出しの機会・方法についてあらゆる可能性を検討しているか、市況を冷静に見ているか、また、このタイミングを逃すことは将来の経営に制限をもたらさないか等々を検討し、執行からの提案に対して速やかに判断できる体制を整えていました。
不透明な市場環境下での執行側からの提案となりましたが、かかる海外市場における株式売出しは、長期的な視点に立って当社の成長戦略に理解を示すグローバルな投資家基盤の構築を可能にするとともに、政策保有株式の潜在的な売却懸念を大幅に緩和し、当社株式の市場流動性の向上を図り、東京証券取引所「プライム市場」の上場維持基準達成にも寄与することが執行から丁寧に説明されました。取締役会としては、「アセット・アセンブラー」モデルによるMSV追求に合致する施策として積極的に評価し、執行側の提案を承認しました。
取締役会の責務がリスク回避を優先するものであるとすれば、市場動向に関する情報の把握が不十分として提案を先延ばしにする判断に傾いていたかもしれません。しかし、私たちの追求するMSVの実現のためには、執行の適切なリスクテイクをサポートすることが求められます。私たちはその時に持ち得る全ての情報と自らの見識に基づき、最善の決定を導くことが責務です。結果的には、当社株価は一時的に低迷しましたが、当初の目的を果たすとともに、下期にはグローバル競合企業との比較において上位クラスのPER(株価収益率)まで回復しました。翻って考えると、あの時に判断を遅らせていたならば、このような結果は得られなかったと考えています。当社の報酬委員会は、本件による一時的な株価低迷により、執行の評価を下げることはしませんでした。毅然とした評価・認識の明示が、執行の適切なリスクテイクをさらにドライブすると考えるからです。
私は、当社グループのガバナンス上の最大の課題を「MSVに向けてタイムリーかつ適切なリスクを執行側が果敢に取り続けられるか」としましたが、これは取りも直さず、私たち取締役会が「その責を引き受ける覚悟を持ち、常に執行とともに走り続けられるか」ということと同義です。これが、私たち取締役会の求める相互信頼に基づく経営であり、「アセット・アセンブラー」モデルによる持続的成長、その結果として必ずやMSVを実現するものと確信しています。
※本事例は、日経ヴェリタス「ディール・オブ・ザ・イヤー2022」のエクイティ部門にて1位に選定されております。
共同社長体制
-
私たち取締役会が現行の共同社長体制こそが最善と判断した理由は、ウィーさんと若月さんが「EPS(1株当たり当期利益)の最大化」と「PER(株価収益率)の最大化」のそれぞれに対してまさに最適な人物であり、この両名による真に対等な協働こそが「株主価値最大化(MSV)」の実現に向けて最善であると判断したことによります。(当社のMSVの考え方はこちらを参照。)
ウィーさんは、航空工学を学び、シンガポールに拠点を置く航空宇宙・防衛エンジニアリング会社をキャリアの出発点とし、20年余りの間にさまざまな要職を歴任後、最終的にはDeputy CEOとして同社の経営に当たりました。また、シンガポール国会議員も務めており、官民にわたる幅広い経験を有しています。2009年からは、アジア合弁事業であるNIPSEAグループの責任者として、アジアを中心に積極的な事業展開を急速に進めつつ、業績不振の事業や会社に対しては抜本的な改革も断行し、NIPSEAグループを当社全体の売上収益の約5割、営業利益の約7割※を占める中核事業へと押し上げました。さらに2019年のトルコBetek Boyaの買収、豪州DuluxGroupの買収においては、当社グループ全体に及ぶシナジー創出に多大なるリーダーシップを発揮してきました。2020年3月には当社の副社長執行役員に就任し、まさに当社のグローバル事業拡大の立役者となりました。
また、若月さんは、法学部を卒業後、日本の銀行を経てグローバル投資銀行へ移り、M&Aや投資銀行業務の要職を歴任した後、日本リージョンの投資銀行部門副会長を務めました。この約20年にわたる経験から、資本市場への深い造詣、企業の成長戦略の実現に係る多様な知見と経験を有しています。2019年11月に当社へ入社し、翌年1月からは当社CFOとして就任直後から資本市場とのコミュニケーションの深化、効率的な長期買収資金の調達に辣腕を発揮してきました。2021年1月にはアジア合弁事業の100%化ならびにインドネシア事業の買収を資本市場に評価される形で仕上げるとともに、共同社長就任前から日本セグメントの収益性改善に向け大胆な提言を行うなど、次世代のリーダーに相応しい姿を十分に私たちに示してきました。
共同社長体制については一般的に、求心力の分散や指揮命令系統の煩雑さによる意思決定のスピードの鈍化が懸念されるかもしれません。しかし、この2人には、実質を重んじる経営を追求する、いわゆる形式主義を排し、決定と行動の迅速化により業績を向上させるという共通の考えが根底にありました。目指す方向を共有していることなども慎重に勘案し、私たちは、この2人の経営手腕の有機的な結合がMSVの実現に資すると判断しました。
若月・ウィー共同社長体制に移行して2年となりますが、その間にウットラムグループに対する欧州自動車用事業・インド事業の譲渡、欧州におけるCromology、JUB、これらに引き続くNPTの買収、株式の海外売出し、日本における機能会社(NPCS)の分社化、希望退職制度「ネクストキャリアプラン」の実施など、将来を見据えた数多くの施策を一気呵成に断行し、MSVの実現を追求してきました。共同社長体制においては、価値観、目標を共有する強固な信頼関係のもと、両名のそれぞれのキャリアに裏打ちされた専門性、強みが大いに発揮され、グループ経営の視野拡大と迅速・果断なコーポレート・アクションに結実してきています。
4月7日の「中期経営計画(2021-2023年度)進捗説明会」において、若月共同社長から、当社の中期経営計画は順調に進んでおり、コロナ禍やウクライナ戦争など、激変する世の中においても予想を上回る成長を遂げている旨をご報告しました。もちろん、これらの災禍のもと、当社においても生産拠点の一時的な閉鎖や原材料の調達途絶などの危機を経験しています。しかしながら、各パートナー会社経営陣の自律的な危機回避策の実施、同時に共同社長のもとでの地域・事業を超えたグループ連携が縦横に行われたことにより難局を乗り越えることができました。これは、まさに若月・ウィー共同社長体制での迅速な意思決定の賜物であり、「アセット・アセンブラー」モデルによるMSV追求に向けた強固な地盤が固まりつつあると言えましょう。
※2020年度のNIPSEA事業の実績値にBetek Boyaの実績値を加えて算出
独立社外取締役の役割、貢献
-
まず初めに、当社は指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を独立社外取締役が占める等、執行と監督の分離を強く押し進めています。監督側である取締役会、とりわけ独立社外取締役が正に「株主の代理人」としての責務を果たすことが、当社のガバナンス体制の成否を分ける鍵となります。
私たち独立社外取締役が株主の皆さまのお考えを確認する第一の場として株主総会があります。皆さまと直接の対話ができることは何よりも重要と認識していますが、定時株主総会は年に1回のみです。従って、共同社長やIR部門からの月例報告および適時の情報共有の機会を設け、当社のみならず競合各社の業績や株価および業界の動向を逐次追いかけるとともに、それらに関するリサーチレポートを通じた情報収集・分析も精力的に行い、常に皆さまの声に耳を傾けています。
また、当社の考え方やグループの状況をお伝えすることが皆さまとのコミュニケーションの第一歩であると考え、適時・適切な開示に努めています。
例えば、統合報告書2022では、当社会長のゴー取締役から、改めて経営の唯一のミッションである「株主価値最大化(MSV)」の理念をお伝えするページを設け、更に対談として、そのMSVの実現に資する役員報酬の構築を巡り、私たちが歩んできた試行錯誤の歴史についても詳らかにご説明しました。また、2021年8月に決定した「欧州自動車用事業・インド事業のウットラムグループへの譲渡」を特集として取り上げ、当社とウットラムグループの本件の取引に関して、特別委員会および取締役会がどのように少数株主利益の保護やMSVとの整合性を吟味してきたかについてもご紹介をしています。
加えて、当社のホームページで、独立社外取締役一人ひとりについて、そのプロフィールや強み、当社の課題へのアプローチ等をご紹介する連載を開始しました。
このように様々な角度から当社の考えやメッセージをお届けすることで、株主や潜在的株主としての投資家の皆さまの当社へのご関心を深めていただき、皆さまからの当社への更なるご意見につながることが、より建設的な対話の礎になると確信しています。
他方、残念ながら株主の皆さまお一人おひとりとお会いすることはかないませんが、より直接私たち取締役会が株主・投資家の皆さまのご意見を理解するべく、筆頭独立社外取締役また取締役会議長として、スモールミーティング(2021年、2022年)やOne on Oneミーティングを開催し、皆さまからご意見をいただくことも行っています。その内容については、当社のホームページにて公開するとともに取締役会においていただいたご意見を共有しています。また、このようなスモールミーティング等では時間に限りがありすべてのご質問にお答えしかねることもありますが、直接的な対話に替えた本企画のような場を通じて、丁寧にお伝えすることを心がけています。このような取り組みが皆さまの当社に対するご評価の一助になればと祈念します。
以上のように、統合報告書、当社のホームページ等を媒体としたコミュニケーション、また、実開催のミーティング等を通じ、株主の皆さまのご意見をしかと受け止め、MSV実現への歩みを進めることにより「株主の代理人」としての私たちの責務を果たしていきます。
最後に、当社の独立社外取締役報酬は、報酬総額の約半分を譲渡制限付株式報酬としています。当社の少数株主でもある私たち独立社外取締役は「株主価値最大化(MSV)」の実現に向けて株主の皆さまと同じ立場にあることを申し添えます。 -
当社の執行は、自律・分散型グループ経営としての「アセット・アセンブラー」モデルを指向しています。これと並び立ち監督の立場にある私たち独立社外取締役も中央集権的なマネジメントの発想はありません。ましてや業務の細部にわたるマイクロマネジメントは執行と監督の分離にも抵触します。現場に執行の権限をより渡すことにより、遠心力はなるべくして強くなりましょう。
他方、執行の強化・スピードアップを進める以上、それと呼応する監督の強化は必須であり、その監督の核心を担う独立社外取締役の責務を果たすべく、どのような取り組みを行っているのかという問いと理解しました。
独立社外取締役が、執行の戦略や状況を認識する上で、私たちは共同社長へ、事業上のトピックスを定常的に取締役会に報告する「共同社長レポート」を求めておりこれが最も基礎的な情報になります。
また、取締役会の場に留まらず、成長戦略議論に特化・集中したオフサイトミーティングや、グループ主要経営陣であるGlobal Key Persons(GKP)をはじめとするマネジメントとの意見交換も随時行っています。これについては、本稿で2023年1月31日に公開した「取締役会の実効性」においてお伝えした通りです。
加えて、事業活動の現場についての理解をより深めるべく現地視察も適宜行っています。例えば、2020年以降では、コロナ禍による制約はありましたが、日本国内の栃木県、千葉県、愛知県の生産拠点、および、東京都の研究・開発拠点、加えて、海外グループではマレーシアなどの生産拠点の視察と現地マネジメントとのディスカッションも行いました。
更に、当社グループ売上高・営業利益の過半を占めるアジア地域事業を率いるNIPSEAグループが年2回主催するグループ・マネジメント・ミーティング(GMM)を通じたモニタリングも行っています。
以上のような取り組みが、取締役会の主要な情報源であり、これらから得られる洞察が取締役会の議論の基盤となります。
しかし、私たち独立社外取締役が果たすべき役割はあくまでも監督であり、グループ事業は徹頭徹尾、私たちが信頼し、私たちが選んだ共同社長のリーダーシップにおいて執行されるべきものです。
私たちは常にグループの最新の情報をキャッチし、直接・間接的に現場を知り、GKPらの声に耳を傾ける努力は一切惜しみませんが、これらはすべて私たちが当社グループの将来を預ける共同社長とのコミュニケーションの適正な密度を保ち、適切な緊張感を持たせるためのものです。
2023年2月28日に公開した本稿の「取締役の人数およびスキル・マトリックス」において、当社の取締役候補者選定に際して、「事業会社経営経験」、「グローバル経験」、「M&A経験」を重視している旨をお伝えしました。この3つの経験を保有している点において、私たちは、執行への過剰な干渉により本来発揮できるはずのスピードを減速してしまうリスク、または、より果断に為すべき判断を穏便なものにしてしまうリスクにも真摯に向き合っています。
当社の唯一の経営ミッションはMSVです。私たちは上記のようなグループ理解を深める努力を続ける一方で、執行と監督の分離、双方の強化を進め、適正なガバナンスのもと、MSVの実現に邁進します。
取締役の人数およびスキル・マトリックス
-
当社取締役会は、株主・投資家の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーに対する責務を認識し、適切な権限行使を行い、当社の中長期的な株主価値最大化(MSV)を実現することに責任を負っています。そのため私たちは、取締役会を信頼の深化を図り得る適正規模、現状11名とし、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、スキル・マトリックスも用いて経験・スキルのバランスを考慮することとしています。
独立社外取締役の貢献はMSV実現に向けた前提条件です。当社の取締役会は、2020年の指名委員会等設置会社へ移行以来、多少の人数増減を経ながらも常に独立社外取締役が過半数となる構成を堅持してきました。これにより、独立社外取締役が自らの知見に基づき、当社グループの持続的な成長を促し、中長期的MSVを図る観点から助言を行う監督機能を果たしています。なお、現在(2023年2月末)の取締役11名のうち8名が独立社外取締役です。更に、非業務執行の取締役会長としてゴー取締役、執行と監督の情報共有の強化を図るべく代表執行役共同社長を兼務する取締役として若月・ウィー両取締役を加えた構成としています。
また、現在の取締役会には、事業会社や金融機関およびプロフェッショナルファームなどの多彩なバックグラウンドを持った取締役が集っており、加えて、国際性、ジェンダーの視点からも十分な多様性を備えた構成となっています。
他方、取締役会のこれらの多様性を作り上げるプロセスについては、当社特有のアプローチがあると捉えています。
私たちは、「先んじて取締役や執行役に対する画一的な後継者計画を作り、それに沿って足りないピースの形に合う候補者を探し絞り込んでいく」という進め方を採っていません。相互信頼に基づき真に実効的な議論の深耕を追求する当社取締役会においては、適正な人数や理想的な保有スキルが先にあるのではなく、経歴や人となりを手掛かりにどのようなパフォーマンスが期待できるのかなどを問い、総合的にその人物が信頼に値するかを見極めることを主眼としています。つまり、徹頭徹尾、人物そのものや人とのつながりを拠り所とした進め方を採っています。
このアプローチを経て、私たちが、ともにMSVの実現を目指す仲間として信頼に値すると得心する人物には共通する3つの経験があります。それらが当社のスキル・マトリックスに掲げる「事業会社経営経験」、「グローバル経験」、「M&A経験」であり、「アセット・アセンブラー」モデルを推進する当社グループにおいて、実際の職歴を通じて得られたこれらの3つの経験はとりわけ重要です。
また、そのような人物にはこれらの経験に裏打ちされた固有のスキル(「ファイナンス」、「法務」、「IT/デジタル」、「製造/技術/研究開発」など)があります。これらの各取締役の高い専門性が余すところなく発揮されることにより、当社取締役会の議論の基盤が形作られています。
しかし、将来に望むべき取締役候補者は、これらの条件によって自動的に絞り込まれるものではなく、あくまでも人のつながりや、十分なコミュニケーションの末に確信される相互信頼よって選ばれるべきものです。
直近の事例として、2022年3月に当社取締役に就任したカービー取締役は、グローバル塗料メーカーでの長きに亘るCEO経験を有しており、その辣腕や「人となり」は私たちもよく知るところでした。また、リム取締役のシンガポール政府系投資会社であるTemasekにおける経験や、シンガポール政界におけるリーダーシップは同じく私たちが実際に目にしてきたものです。最終的には、指名委員会が本人との直接のコミュニケーションを重ね候補者として選定しましたが、このような実際の人のつながりに基づく洞察は極めて重要な示唆となりました。つまり、MSVの実現に向け当社の「アセット・アセンブラー」モデルを推進するために必要不可欠な仲間を探し求め続けた結果が、現在の取締役構成となりスキル・マトリックスとして現れているのです。
この私たちのアプローチは、当社グループのM&A対象の選定においても同様です。世界中の塗料メーカー等をロングリストとし外形的要件により絞り込んでいくのではありません。既存事業および「Paint++」事業領域への拡大を進める中で顔の見える相手を増やし、彼らとの十分なコミュニケーションに基づき、真に信頼すべき相手を見極め、パートナーとして手を結んでいきます。これが自律・分散型経営である「アセット・アセンブラー」モデルにふさわしい考え方であると確信しています。
当社グループの成長に伴い、取締役会は今以上にその視座を押し上げ、当社の将来を指し示すことが求められます。当然、必要な監督機能の質も刻々と変わっていきます。それに応え得るチーム作りへの努力を絶え間なく続け、これからも私たち取締役会は進化していきます。
取締役会の実効性
-
株主価値最大化(MSV)を経営上の唯一のミッションとする当社の「取締役会の実効性」は、中長期的には当社の株主価値そのものによって評価されるべきものです。
このMSV実現に向けて、私たちは信頼をベースとしたグループ経営が最善であると考えており、具体的には「アセット・アセンブラー」モデルであると確信しています。当然、取締役会においても、取締役相互および執行との信頼の深化が不可欠となり、まさにこれが当社の「取締役会の実効性」をさらに向上させる鍵となります。また、これが現時点における「取締役会の実効性」を計る尺度にもなると認識しています。
この相互信頼を醸成するために、各取締役は取締役会や各委員会のみならず互いに直接コミュニケーションを密に取っています。また、取締役会の開催後には独立社外取締役会議を都度開催し、取締役会の進行や議論内容についての意見交換に加え、グループ主要経営陣であるGKP(Global key Persons)をはじめとする執行側からの声を直接聞くことも適宜行っています。例えば、監査委員会では各パートナーカンパニーのマネジメントチームとの対話を継続的に実施しており、2022年には16回のセッションが設けられました。このようなコミュニケーションから得られる現地における成長施策の手応え、課題解決に向けた示唆は取締役会にも共有されております。これらにより、私たちが自律的・分散型経営を指向しながらも、事業実態を踏まえた実効的な成長戦略議論を行うことを可能にしています。このように集約された意見を共同社長両名やゴー会長との意見のすり合わせに活かすことが独立社外取締役としての貢献の礎であり、ここから紡ぎ出される取締役会の議論が最終的な決定の質を高めていくと考えます。
また、私たちの「取締役会の実効性」向上へ向けたこのような取り組みの進捗については、第三者機関である株式会社ボードアドバイザーズにより他社比較等も含めた客観的な評価を毎年行っております。2022年の実効性評価は、総評として、「取締役会の実効性は概ね確保」され、取締役各自の異なる知見を活かしながら「執行を後押しする観点から活発な議論に臨んでいる」とし、一定の進捗を見たと認識しています。一方、更なる取締役会の実効性向上に向け、「独立社外取締役の貢献」が今まで以上に求められることも確認されています。その結果を真摯に受け止め、私たちの課題を常に見直し改善を重ね、MSVの実現、更なる飛躍へ向け邁進していきます。 -
当社の成長戦略は大きく2つあります。1つ目は既存ビジネスのオーガニックな成長、2つ目は新たなアセットを買収によりアセンブルするインオーガニックな成長です。
この2つの成長を実現するためには、適切な資本の調達とともにビジネスポートフォリオの視点が不可欠です。例えば、既存ビジネスの強化に投資を行うのかまたは、新たな買収を行うか、もしくは既存ビジネスの売却か、様々な状況を俯瞰的に捉え当社の成長へつながるベストな判断を執行側ができるように後押していくことが求められます。
塗料・コーティングに関するグローバル市場においては、当社を含めたグローバル企業10社を足し合わせてもシェアは50%に満たず、残り半分は中小のローカル企業等が占めており、当社の拡大の余地は依然として大いにあります。さらに、当社が「Paint++」という言葉で表現している周辺市場は塗料市場の約3倍と言われています。これらをグローバルマーケットにおける当社グループの成長領域として視野に入れ、ビジネスポートフォリオを冷静に分析し投資判断を最適化していくことが、当社取締役会における「成長戦略議論の充実」に資すると考えます。
2022年8月に開催したオフサイトミーティングでは、グローバル競合他社の戦略との比較において当社の独自性・優位性を検証するとともに、周辺業種も含めて当社の「アセット・アセンブラー」モデルの位置づけを見直すなど、当社の成長戦略について徹底的な議論を行いました。共同社長ら執行が推進する「Paint++」戦略における当社グループのポテンシャルや、その実行のための真に適切な資金調達の在り方についても議論が深耕され、私たちのMSVへのロードマップをより精緻なものにすることができました。これらの成長へ向けた共通認識の醸成や課題共有の深化は、取締役会における個々の事案の審議の質を向上させることにも活かされています。2022年の取締役会実効性評価においても「戦略をじっくりと議論する機会を持った」ことは「株主価値最大化(MSV)を目指す方針が共有され」た上で「中長期の経営戦略など重要な審議事項について概ね議論されている」と高く評価されました。
当社グループのガバナンス上の最大の課題は、MSVに向けてタイムリーかつ適切なリスクを執行側が果敢に取り続けられるかにあります。私たちの取締役会は、上述の相互信頼の下、執行側から必要な情報のアップデートを常に受け、MSVに向けた執行側のリスクテイクをサポートする体制の深化に努めています。